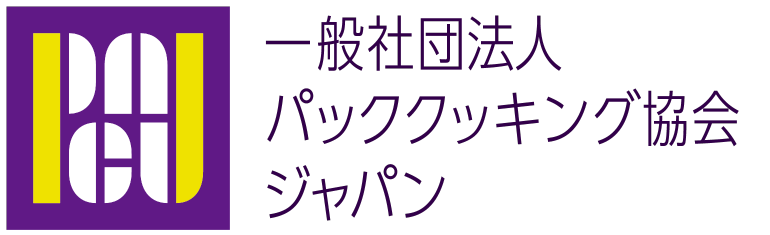夏休み期間を利用して
パッククッキング協会ジャパン認定講師 寺尾華菜子さんが能登支援として
パッククッキングセミナーを開催してきました。
報告を受けて、こちらでも記載しておきます。
能登支援パッククッキングセミナーは、四国災害ボランティアネットワークさんから依頼を受けてでのものでした。
四国災害ボランティアネットワークさんは、継続的に能登での支援活動をされています。
昨年1月能登町の炊き出しの際、水がない状態での炊き出しに大変苦労されたそうです。
皆さんは、炊き出しってどんな状態で開始されると思いますか?
災害のセミナーで参加者から聞こえてくるのが、少し待てば炊き出しの支援があるはず。という安易なお考えです。
場所によっては、確かに支援がすぐ開始される場合もあると思います。
炊き出しは、大鍋で大量調理します。
ほとんど普段のごはん作りと変わらないんです。
炊き出しには、大鍋の洗い物など大量の水を必要とします。
まだライフラインが整っていない状況の炊き出しは、本当に大変です。
*基本的には災害時の炊き出しは、ライフラインが整って開始されます。
もし、パッククッキングであれば洗い物はでません。
たくさん一気に調理するのではなく、それぞれのごはんを袋で調理するという手間はあります。
ですが、指導があれば、パッククッキングの経験があれば避難所にいる皆さんと一緒に作ることができる調理法です。
炊き出しは、誰にでも調理はできないと私は考えています。
家族分4人程度の調理はできても、30人50人と多ければ、多いほど経験がなければ、大量調理は難しいです。
調理を指導するリーダーが現場にいなければ、難しいでしょう。
より早く開始できるのはパッククッキングではないですか?

夏休みに子どもたちの楽しみになるようなセミナーとして
未来の子ども達の食を担う手法として、とっても好評だったようです。
パッククッキングは、災害時の調理法ですが、普段していないことは「いざ」にはできません。
パッククッキングは普段使いできる調理法です。
長年、調理を指導してきた私が、自信を持って伝える普段使いできるレシピがあります。
9月は、防災月間です。
今一度、意識を高め災害時の『食』について考える機会にしてください。

パッククッキング協会ジャパン 池田奈央